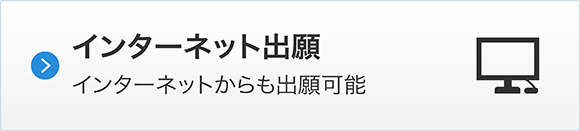宮城学習センター 客員教授
尾崎 彰宏
(専門分野:美学・西洋美術史・芸術理論)
1888年、日本人にもっとも人気のある画家のひとりファン・ゴッホ(1853~90)は、喧噪のパリを脱出して南仏のアルルに向かいました。彼にはアルルが「日本」に思えたからです。ゴッホにとって日本は、芸術の王国として憧れの地でした。ゴッホが浮世絵の蒐集家であり、それを熱心に自分の芸術に取りいれていたことはよく知られています。
歌川広重(1797~1858)の名所江戸百景をあらわした《大はしあたけの夕立》(図1)などは、図柄をそっくり模写しています。激しい夕立の中を大はしを渡る、人影、小舟、対岸の風景が画面いっぱいに拡がっています。ゴッホはそれを額縁に入れた絵画として模写しています(図2)。


出展:Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
そして額にはゴッホが一所懸命書いた漢字がつづられています。和紙に刷られた浮世絵を西洋の油絵に変えているわけです。日本的な感性によって西洋絵画の伝統を変容させようとするゴッホの執念ともおもえる情熱が伝わってきます。
それにしても、どうして広重の浮世絵をこれほど熱を入れて模写したのでしょうか。画面を斜めに横切る橋の構図、どこから眺めた視点なのかはっきりしない曖昧さの魅力、明るい色彩、激しい驟雨の描写に魅せられたから、というのがこれまでの理解です。
もちろん、そうしたこともあったでしょう。しかしそれにもまして、たたきつけるように降る雨に魅せられたのではないでしょうか。降りしきる雨に時間の流れを感じたのではないでしょうか。降りしきる雨とともに時がすぎ去っていくという感覚は、キリスト教の衰退とともにもたらされる死への絶望、罪悪感とは無関係のものです。つまり、すぎ去っていくものの中に死の表象ではなく、美の表象を発見したのです。
すぎ去っていくこと、はかなさこそが美しいという感性です。桜と雨を人の生と重ねることで、悲しさのなかに美を見いだしたあの有名な和歌と通じあうものがあります。「花の色はうつりにけりないたずらに、わが身世にふるながめせしまに」。
地理的にも遙かに隔たり、宗教的にもいちじるしく異なった文化の欧州と日本が互いに大きなインパクトを与えるというのは、両者の感性に共通性があったからでしょう。だからこそ、ゴッホは浮世絵からインパクトを受け、新しい創造への糸口を見いだせたわけです。
20世紀最大の文化人類学者であるレヴィ=ストロースが、浮世絵によって欧州は、新しい感性と出会ったと言ったのは、まことに鋭い直観です。いつの時代にあっても、触発的な文化は、武力による戦争によってではなく、異文化との遭遇によって激しい火花を発し、変容をとげることで新しい果実が誕生するのです。
宮城学習センター機関誌『ハロー・キャンパス』第123号(2022年10月発行)より
公開日 2023-02-17 最終更新日 2023-02-17