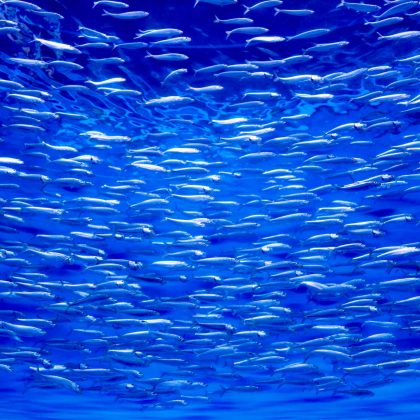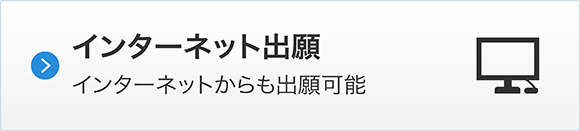放送大学東京渋谷学習センター 客員教授
東京大学 名誉教授
長谷川 まゆ帆
(専門分野:フランス近世史)


みなさんは、18世紀半ばに『ペルー人女性の手紙』(1747年/増補改訂版1752年)を出版しベストセラー作家となったグラフィニ夫人(1695-1758)をご存じだろうか。
18世紀は「啓蒙の世紀」と呼ばれるが、手紙や新聞、雑誌、戯作を含む多様な書籍や図像が流通し、虚構の物語が行き交う時代でもあった。
人々のコミュニケーション回路が緊密になるとともに、「見る」「見られる」関係が広がり、珍品への好奇心、他者への関心も高まっていた。
この時代には、ヴォルテールやルソー、ディドロのみならず、物理学に精通したデュ・シャトレ夫人のように、「書くこと」を通じて女も「啓蒙」への参画を試みている。
まさに現代のインターネットの普及にも匹敵する社会変動の時代だったと言える。
「啓蒙」というと、20世紀の暗い歴史もあり、あまり良い印象を抱いていない人も多い。
しかし従来の平板な理解とは異なり、今は、ロジェ・シャルチエなどの開拓を経て「書かれたもの」と実践との間を問う社会史研究がさかんになり、18世紀史は俄然おもしろくなってきている。
わたしが最近気になっているのは、この時代に意識的に論じられていく「共感sympathy」という語彙についてである。
たとえば、スコットランドの啓蒙思想家アダム・スミス(『道徳感情論』1757年)やデヴィッド・ヒューム(『道徳の原理論』1751年)がまさに「共感」を同時代人として論じている。
スミスによれば、「共感」とは「自分とは異なる他者の感じている悲しみをその人の身に自分をおいて想像するconceive」ことであり、感情を伴って他者の「気持ちfeeling」を理解する過程だった。
スミスもヒュームも「共感」を宗教的な意味での「慈悲misericorde」とは区別しつつ、理性を介して可能になる人間の得難い能力とみなしていた。
グラフィニ夫人は、遠いインカ帝国の滅亡の歴史を綴った歴史書『インカ皇統記』(仏訳版)に触れ、そこから着想を得た。
その上で、スペイン軍に拉致された太陽神殿の巫女ジリアを語りの主体に、スペインに幽閉された王子/許嫁アザへのジリアからの愛の書簡という設定のもと、ペルー人の女の運命をまとめあげた。
夫人はフランスの圧力の下に滅びつつあった生地ロレーヌ=エ=バール公国からの自身の出奔を、ジリアの故郷喪失の悲劇に重ね合わせてもいて、ジリアに異国の地フランスの社交会を批判させることで、他者の声を通じた文明批判を行っている。
自分とは異なる他者の歴史に学ぶとともに、他者の身に自分をおいて「気持ち」を想像しているのである。
加えて物語は「修道院か結婚か」という当時の女の宿命とは異なる道(友愛に生きる)を指し示し、「いまここにあることの喜び」を語って終わっている。
啓蒙期の表象を感情の観点から時間の中で考察することは、啓蒙とは何だったのかを改めて問い直すことである。と同時に、過去との近さと隔たりを通じて、わたしたち自身の現在をよりよくわかるようになっていく過程でもある。
というわけで、現代から過去に問いつつ、18世紀史の特質を一緒に学び考えていきましょう。
東京渋谷学習センター機関誌『渋谷でマナブ』2022年10月発行(第16号)より
公開日 2022-12-16 最終更新日 2022-12-16