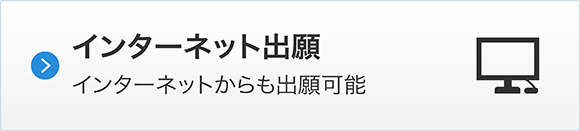加藤 由美
宮城学習センター 客員教員
-683x1024.jpg)

私が担当する課外授業ゼミは「地域で自分らしく生きる」をテーマに、地域包括ケアシステムや地域共生社会の切り口から考察しています。
昨年は、補助テキストとして正岡子規の「病牀六尺」の一部を取り上げました。
本稿ではこれに基づき、子規が家庭における「介抱」(今の言葉で言えば「在宅ケア」)についてどのように考えていたかを紹介したいと思います(「病牀六尺」からの引用は傍点を含め原文ママ)。
正岡子規は慶応3(1867)年に生まれ、明治35(1902)年にその短い生涯を閉じました。
彼は若くして結核という病を得、そこに脊椎カリエスも重なって、晩年の数年間は寝たきり状態でした。「病牀六尺」は子規の最晩年の随筆集です。
この中で子規は「介抱」を論じる際に「看護」という言葉を多用するとともに、今日我々が「介護」と呼ぶ諸々の行為(例えば「病人の傍で看病しながら食物を調理する」「蒲団が重たさうだと思へば軽い蒲団に替へてやる」など)も同じ文脈で扱っています。
すなわち子規の言う「介抱」とは、「看護」と「介護」を併せ持つ「ケア」の概念に包含されると考えます。
死の2ヶ月前となる明治3年7月16日、子規は「死生の問題は大問題ではあるが、(中略)それよりも直接に病人の苦楽に関係する問題は家庭の問題である。介抱の問題である。(下線は加藤)」と記しています。
彼の生きた時代、人が生まれ・療養し・死にゆく場所は「家庭」でした。子規が「介抱の問題」は「家庭の問題」であるとした所以です。在宅ケアのあり方が人生の質(QOL)を左右するのは、明治も令和も何ら変わらないのです。
また、子規は次のようなことも述べています。
「病気の介抱に精神的と形式的との二様がある。(中略)もしいづれか一つを択ぶといふ事ならばむしろ精神的同情のある方を必要とする。(中略)介抱人に同情さへあれば少々物のやり方が悪くても腹の立つ物ではない(下線は加藤)」。
この「同情」とは、今でいう対人援助の基本的態度(傾聴、共感、受容など)に他なりません。ケアの知識や技術もさることながら、まずは相手に寄り添う気持ちや姿勢が不可欠であるという点が、現代と全く同様であることに深い感銘を覚えます。
面白いことに、当時すでに「家庭の事務を減ずるために炊飯会社を興して飯を炊かす」という先進的アイディアが世に出ていたようで、子規は「それは善き考である」と大賛成でした。
病人の居る家庭が炊飯会社を利用すれば、家族は飯炊きにかける時間や労力を「精神的な介抱」へ振り向けることが出来る、という理由からです。
斯様に柔軟な考えの持ち主だった子規ではありますが、「介抱」は「女子」が一手に担うべきものという当時の価値観が彼の中にも厳然として在りました。
しかしながら、当時と今日の価値観の相違は一旦置いて、ケアの本質を見極める視点で臨めば、家庭での「介抱」すなわち在宅ケアに関する子規の見識は、百年余の時を経てなお示唆に富んでいます。
価値観やシステムは時代とともに変化しますが、そのような中で私たちは一貫して不変の事柄を見出し、大切にしていきたいものです。
引用文献:正岡子規「病牀六尺」岩波文庫.1987.第29刷
宮城学習センター機関誌「ハロー・キャンパス」第127号(2023年10月発行)より
公開日 2024-01-23 最終更新日 2024-01-23