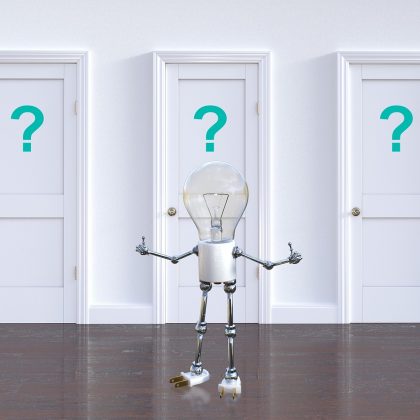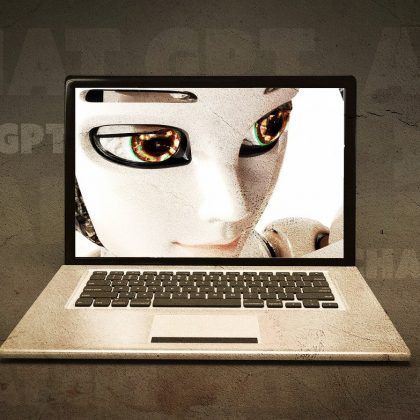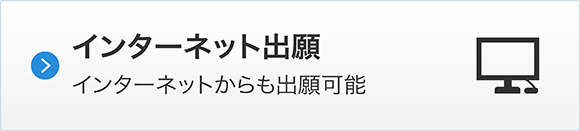秋田学習センター客員准教授 大西 洋一


19 世紀の歴史家トーマス・マコーリーがイギリスは「人類の聖なる避難所」であると語っていたように、母国を追われた多数の人々がこれまで英国に安住の地を見出そうとしてきた。
宗教的・政治的迫害を逃れてきたユグノー教徒などの大陸のプロテスタントやロシアおよび東欧諸国のユダヤ人たち、そして飢饉による経済的困窮のために国を離れたアイルランド人移民など、苦しむ人々を受け入れる寛容さを英国民は常々誇りとしてきたのだ。
だがその一方で、増え続ける移入者が社会的な摩擦を生み、人種的偏見と差別的待遇が生じて多くの軋轢と衝突が人々の間に起こったというのも多文化・多人種の英国の歴史的現実である。
最近では2016 年のEU(欧州連合)離脱をめぐる国民投票の際に、英国に押し寄せる移民の問題が争点となったことが記憶に新しい。
さて、2022 年2 月に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻で祖国を追われた人々の数は、770 万人を越えるという(国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)ホームページの6 月16 日現在のデータより)。
ヨーロッパの近隣諸国をはじめとして世界各国に彼らは避難しているが、イギリス政府もまた「ウクライナの人々に住まいを」(”Homes for Ukraine” Scheme)という支援事業を立ち上げて引受人を募り、名乗り出た一般家庭等で避難民を受け入れている。
対策を立てるのが遅いとの批判はあったが、この事業により発給されたビザは6 月14 日現在で約88,000 件に達した。4 月中旬に放送されたBBC のニュースでは、私がかつて住んでいた北イングランドの都市リーズ近郊の小さな町で避難家族を迎え入れている様子を伝えていた。
このように、英国全土においてウクライナからの避難者があたたかく受け入れられていることは想像に難くない。
しかしながら、このニュースを見た数日後に私は愕然とした。イギリス政府が4 月14 日に発表した「庇護申請者」(asylum seeker、庇護(asylum)を求める人(seeker)、すなわち「亡命希望者」のこと)に対する施策を知ったためである。
今も紛争や人道危機が続く国々(たとえばアフガニスタンやシリアやイラク)から来た難民にとってイギリスが魅力ある目的地であることにつけ込んで、人身売買業者が多数の「庇護申請者」を小型ボートやトラックで不法入国させることが近年大きな国際問題となっていた。
その抑止策として、非合法な手段でイギリスに入った亡命希望者の一部を片道切符のフライトでアフリカ東部のルワンダに送り、そこで難民申請の審査手続きを行う(その後で英国に戻されることはない)というのである。
1994 年の民族虐殺に対する対抗で生まれたポール・カガメ大統領の政権が独裁的性格を帯び、今では人権状況に関して大きな懸念が生まれている、あのルワンダである。
この施策に対しては、イギリス国内でもカンタベリー大主教や野党の労働党および多数の人権擁護団体などからその非人道的な政策を非難する声が上がった。
しかし政府はこの計画を推し進めて、ルワンダへの第一便を6 月14 日に出発させる予定であったが、欧州人権裁判所の介入による法的措置によりすんでのところで中止となった。だが、この「庇護申請者」をめぐる問題は今後も予断を許さない状況である。
私が演劇研究のために2016 年に渡英した際には、難民が母国で感じた不自由と不寛容を物語る演劇や、シリア難民自らが自らの苦境をユーリピデスの「トロイアの女たち」に仮託して演じた演劇を観て、イギリスの人々の難民問題に関する深い関心を目の当たりにしてきた。
それだけに、戦火のウクライナから命からがら避難してきた人々に対して支援の手を差し伸べる一方で、今なお危機にある様々な国々からこちらも命を賭して英国に渡ってきた人々を門前払いするというイギリス政府の政治的判断には大きな違和感を感じざるを得なかった。
6 月20 日は国連が定める「世界難民の日」であり、今年世界の難民の数は1 億人を超えてしまったという。我々が支援の手を差し伸べる時には、さらにその向こうにも手が届かない存在がいることを忘れてはならないのだ。
秋田学習センター機関誌「ばっけ」第102号(令和4年7月発行)
公開日 2022-11-18 最終更新日 2022-11-18